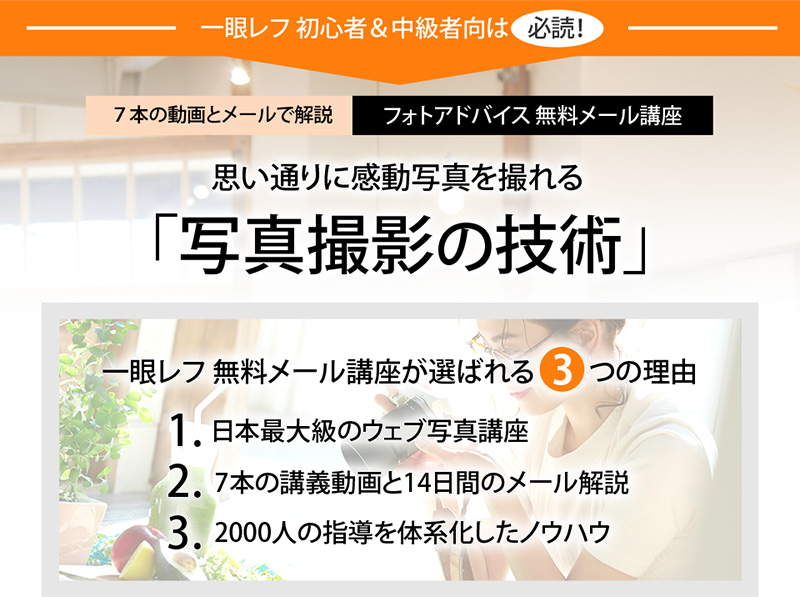「おすすめ写真集」写真家ご夫妻がお気に入りの6冊を徹底レビュー

写真家を写真家たらしめる優れた技術はもちろん、哲学から生き方まで、大切なエッセンスがぎゅっと凝縮されている「写真集」。ここには「写真ってなんだろう?」という問いへの答えが詰まっています。写真家のご夫妻、宇井眞紀子さんと平林達也さんが、オススメの写真集6冊をそれぞれの視点から教えてくれました。
宇井眞紀子さん
写真家。1992年からアイヌ民族の取材に取り組み、写真集『アイヌときどき日本人』で第7回「週刊現代ドキュメント写真大賞/国内フォト・ルポ部門賞」を受賞。『ASIR RERA(アシリ・レラ)』で第4回「さがみはら写真新人奨励 賞」を受賞。第28回「東川賞特別作家賞」受賞。第1回「笹本恒子写真賞」を受賞。
平林達也さん
写真家。写真プリント企業「フォトグラファーズ・ラボラトリー」代表取締役。写真集に『成長の代価』(写真工業出版社)や『高尾山~霊気満山~』(窓社)などがあり、全国各地のニコンサロンなどにて数多く個展を行う。
Contents
『化外の花』(太田 順一)
タイトルにある「化外(けがい)」とは、「天子様の教えの届かないところ。王権のおよばないところ」のこと。これは殺風景な湾岸の埋立地、工場地帯、都市の辺境のあたりなどを、太田順一さんが歩きながら撮影した写真集で、日本写真協会賞の第1回作家賞を受賞しました。
新型コロナウィルスの感染拡大から、家にこもることが増えましたね。今は撮影に出かけるといっても、近くをお散歩をすることくらいしかできません。でも、そんなときはこの写真集がきっと参考になるはず。自分の目線で、身近なものを発見しながら撮っていった写真がたくさんあるからです。



『メメント・モリ』(藤原 新也)
1983年に刊行されて以来、大変な話題になり、30年以上にわたって読み継がれてきたロングセラーの写真集です。「メメント・モリ」とは「死を想え」という意味。ペストがはびこった中世末期のヨーロッパでよく使われた宗教用語なのだそうです。
1970年代から80年代に、インドをはじめとした世界各地で藤原さんが撮影した74点の写真に短い言葉がつけられています。

「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ。」
「その景色を見て、私の髑髏がほほえむのを感じました。」
「黄色と呼べば、優しすぎ、黄金色と呼べば、艶やかに過ぎる。朽葉色と呼べば、人の心が通う。」
「母の背は、曠野に似る。」
「虫がさわぐ。」
「真最中。」

藤原さんご自身は、汚れてメロメロになるまで何年経ってもめくってほしいというのが願いだとされています。大事にしまっておくのではなく、何度も見返すことを目的に作られたことを思えば、B6判に近い小さめのサイズも納得です。

私は「ニンゲンは犬に食われるほど自由だ。」という写真が衝撃的でした。犬が人を食べている写真があるのです。日本では病院のベッドで死ぬ感覚しかないですが、犬に食べられることも自由だと言えば自由なんだなと思いました。
藤原さんは、2020年3月に『日々の一滴』(トゥーヴァージンズ刊行)を上梓されています。こちらも『メメント・モリ』と同じく写真と言葉で表現されているので、もし機会があれば、こちらもお手にとられてみてはいかがでしょうか。
『Henri Cartier-Bresson』(アンリ・カルティエ=ブレッソン)
アンリ・カルティエ=ブレッソンは、1908年にフランスで生まれた偉大な写真家です。1947年にはロバート・キャパらとともに写真家集団「マグナム・フォト」を結成し、20世紀写真史に大きな影響を残しました。
ブレッソンが生きた1900年代は大型のカメラを使って撮るのが一般的でしたが、彼は新しく登場した小型カメラを使って、いわゆるスナップショットを撮りました。その作風は「決定的瞬間(image a la sauvette)」として有名です。
ブレッソンは街中を歩き、何かを演出をするわけではなく、ありのままを撮影しました。でも、すべてのものが完璧な配置。すべてがその一瞬でしかありえない、その瞬間を的確に捉えているのです。彼は写真家になる前は絵画を学んでいたそうで、みごとな構図には絵画の素養も生きているのかもしれません。
「一瞬を逃さない」というのは「待つ」ということでもあります。「こういうことが起こればいいな」「こんな感じはどうだろう」と自分の中でイマジネーションを持っていることも大事かな、と思います。
ブレッソンはほとんどの作品を50mmの単焦点レンズで撮りました。そういう意味では、標準単焦点レンズで写真の練習をされている方にも参考になるんじゃないでしょうか。この写真集を見れば、「50mmでこんな画が撮れるんだ!」と、きっと驚かれるはず。ひきの絵は広角で撮りたいと思うものですが、50mmでも十分広い絵が撮れることを教えてくれます。
彼の作品で最もよく知られるのは、水たまりの上をぴょんと飛び跳ねた人の、着地するかしないかの瞬間を捉えた写真「サン=ラザール駅裏」。




最後にブレッソンの言葉を引用します。「写真をとることは、一瞬のうちに消えて行く現実の表面にありとあらゆる可能性が凝集した瞬間に息をとめるということである」。そして、「写真を撮るに際しては、常に、対象と自己に大して最大の尊敬を払わなければならない」とも書かれています。

『みさおとふくまる』(伊原 美代子)
とてもかわいらしい写真集です。伊原さんはずっと自分の実のおばあちゃんであるみさおさんを撮り続けていました。
撮り始めて少しした頃、土と共に生きているおばあちゃんの元に、子ネコがやってきたのだそうです。福の神がきて、全てが丸く収まるように、という願いを込めて、おばあちゃんが「ふくまる」と名づけたんだとか。
写真集には、毎日の畑仕事に精をだすおばあちゃん、いつも一緒にいるふくまる、うつろう季節や農作物が写っています。自然の恩恵をよろこびながら暮らすおばあちゃんの姿は、孫の目から見た身内だからこそ撮れるんだよね、と思わせる写真がいっぱい。


『弁造 benzo』(奥山 淳志)
タイトルにある「弁造」というのは、北海道の開拓民の最後の世代として、小さな丸太小屋で暮らした方のお名前です。
畑を耕したり、庭を整えたりして暮らす弁造さんに奥山さんはすっかり魅了され、10年以上彼のもとに通いながら撮影されました。最初は自給自足の生き方をしている弁造さんに興味があったみたいですが、次第に生き様や人生へと興味がうつっていったようです。
奥山さんは、弁造さんが生きているときはご本人を撮ることを主体にしていましたが、その没後は家や遺品、画家になりたかった弁造さんが描き続けた下絵(エスキース)を撮りました。このようなエスキースが作品として入ってくることによって、弁造さんの人生が深く物語られているような気がします。


この写真集はどこの出版社も通さずに300部限定で制作され、すでに完売しています。でも、もしかしたらどこかで巡り巡って手に入るかもしれない、そんな一冊です。
『An Uncertain Grace』(セバスチャン・サルガド)
ダイナミックな構図が見どころの豪華な写真集です。タイトルの言葉は“神の恩寵”という意味らしいのですが、日本語訳がなく、正確な発音がわかりません。
サルガドは1944年ブラジルに生まれ、パリに移り住んだ方。世界の貧困や労働などを迫力ある描写で世界に発信してきた社会派写真家です。1980年代よりユージン・スミス賞やハッセルブラッド国際賞など数多くの賞を受賞してきました。
たとえば表紙の写真、これはどこだろう、南米のアマゾンでしょうか、子どもたちが天使みたい。ポーズも自然体で、まさにありのまま。一体どういうポジションから撮ったらこんな風に撮れるんでしょう? そう不思議に思うような作品がここにはたくさん収められています。







ここまでご紹介した6冊は、手に入らないものもあるのですが、「東京都写真美術館」(東京都目黒区)の図書室などでご覧になれるかもしれません。
あるいは、「日本カメラ博物館 JCII Camera Museum」(東京都千代田区)という手もあります。館内の図書館に、数多い写真集やカメラ雑誌など古いものから新しいものまでたくさん収蔵されています。
機会があれば、そうしたところで探してみるとかなりのものが見られるはずです。機会がありましたら、ぜひお手にとってみてください。